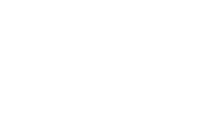道教委は道立学校の冷房設備について、25校の特別支援学校と幼稚部、小中学校を有する学校を優先的に整備し、高等学校については校舎の老朽化に伴う大規模改造計画に合わせて整備を行っていく方針です。2024年度大規模改造計画の設計校は5校で2027年度から空調設備が使用開始予定です。しかし、すでに改造工事に着手した高校については冷房設備の整備工事が次期の大型工事までされないことがわかりました。大規模工事は建築後20年と35年をめどに実施、その後の工事は47年目になります。
丸山はるみ道議は、工事に着手した高校で空調設備工事のための設計変更を行なわなかった理由を質しました。
道教委は設計変更で工事に遅れが出ると弁明し、暑さ対策については、2024年7月までに全道立高校の普通教室に簡易型空調機器を整備していると答弁。
丸山道議は「次の大規模工事まで何年も待たされる。熱中症での保健室利用、救急搬送が増えている事を重く受け止め、大規模改造待ちの冷房設備の整備方針の見直しとともに、簡易型空調機器ではなく、業務用クーラーの設置推進を進めるべき」と強調しました。