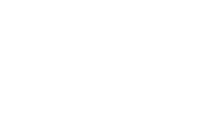日本共産党道議団は、道外視察のため5月13日から16日、鳥取県、岡山県、滋賀県、大阪府を訪れました。滋賀県では、一般社団法人近江鉄道線管理機構が、上下分離方式で鉄路を存続させた取組を聞きました。
琵琶湖の南東部、約60㎞を走る近江鉄道は、今年4月1日から県や沿線自治体でつくる「近江鉄道線管理機構」が線路や駅などを保有する一方、近江鉄道が列車の運行を
担う「上下分離方式」に移行しました。
1994年以降赤字が続き、滋賀県に協議を申し入れ
西武グループ傘下の近江鉄道が県に申し入れたのは2016年。沿線市町も含め勉強会を開始。3年後に有識者も加わり地域交通再生協議会を設置。担当課長会議を月に1〜2回は実施など、協議を密に重ねました。
アンケートは当事者である沿線住民を対象に
地域で鉄道存続の合意を醸成するためには日常生活で利用する可能性が高い沿線住民を対象にアンケートをとる必要があると判断したと言います。また、利用の少ない区間でもつながっていることに価値があると考え、ぶつ切りにせず存続することを追求しました。
事業者や行政が地域と一緒になって鉄路存続のために知恵を出し、努力した結果の「新生近江鉄道」が住民の生活を支えています。