知事の姿勢が問われます!
丸山道議は11月14日、決算特別委員会知事総括で、「子育て支援」「性の多様性」「道民との対話」について、鈴木知事の姿勢を質しました。
昨年度(2023年)北海道の合計特殊出生率は、全国ワースト2位に転落しました。
子育て支援について道民の関心第一位は、医療費助成です。
丸山道議は「道内各市町村が自主財源で、助成枠を拡大している。北海道の医療費助成も拡充すべき」と知事に求めました。
知事は「全国一律の助成制度の創設を国に求めていく」と、かたくなにその姿勢を崩しません。
丸山道議は「公平性の確保が必要と言うなら、北海道が率先して道内市町村で生じている格差を是正すべき」と知事の決断を強く求めました。
なぜ?道営住宅入所で差別
道営住宅への同性カップルの入居が、パートナーシップ条例を制定する市町村に限られることから、10月に行われた北海道市長会総会で道内でのパートナーシップ制度の導入を求める意見書が議決されました。
市町村で対応に差が出ており全道一律の対応を行うためにも、道による制度導入が必要との理由です。
丸山道議の質問に、環境生活部は「要請書を重く受け止めている」と答弁。しかし、鈴木知事は「市町村の取り組みが進むよう支援する」と要請書に背を向ける答弁です。
鈴木知事自ら道内の先進事例を視察する「なおみちカフェ」は1期目から数えて200回を超えています。一方で公募型による道民との対話の場は開催していません。丸山道議は「カフェとは名ばかり、さながら会員制サロンのよう」と批判。困難を抱える道民の声が届く道政の実現を求めました。

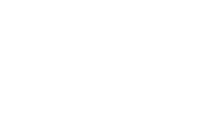


.jpg)


















